スーパースラントノーズのスぺシャリティスポーツ
青木 秀敏
―― 最初はセレステ次期車だった
1977年、セレステの大規模なマイナーチェンジ計画がスタートし、ノーズはそのままに、リヤ周りを大幅に形状変更することとなった。また、これと並行して2年後に発売予定のランサーEXをベース車とするセレステ次期車の開発も始まったが、マイナーチェンジ計画の方はデザインモデルを作ったものの途中で中止されることとなった。次期車は「ホット&スポーティ」をキーワードとしていながら後席居住性の向上を求められていた。また当初はターボやリトラクタブルヘッドランプなどの採用は俎上に上がっていなかったこともあり、様々なデザイン提案を行ったもののいまひとつ性格が定まらず、紆余曲折の内に時間が過ぎていった。

セレステ次期車として検討されていた初期のデザイン
―― クライスラー提案
そんな折の1978年4月担当者の配置換えがあり、それまでの貝淵、河野、岩本に私を加えた新チームで担当することになった。それから一月ほど経過した頃、当時の提携先のクライスラーから1/1モデルが送られて来た。それはロータス・エスプリ似のイメージで、日本で流行の兆しがあったリトラクタブルヘッドライトを採用、ベース車の13インチタイヤを14インチとし、セレステよりホットなイメージとしていた。この車はクライスラーでの販売が前提となっており「こんな車にしてほしい」という提案であった。

クライスラー社の提案モデル
―― ベース車の変更
クライスラー案は粗削りではあったがインパクトがあり、その方向は「我が意を得たり」と言えるものでもあった。我々もこれを契機にリトラクタブルヘッドライトや、バンパー下端までワンモーションのスラントノーズなどをモデル化し、よりホットなイメージを目指した。しかしランサーEXベースでは車体、タイヤサイズともに小さく、スポーティで迫力あるデザインの実現には限界を感じていた。こうしたデザイン部門の状況だけでなく、クライスラー提案の影響もあったのであろう、ベース車を上級の2代目ギャランΣに変更し、リアルスポーツカーにも比肩し得る車を目指す方針となった。この時、経緯は不明だがウインドシールド付け根位置をベース車よりも20mm後退させることになり、わずかではあるがロングノーズ、ショートデッキのプロポーションにすることができた。またターボ搭載が決まったのもこの頃だったと思う。

クライスラー社の提案に刺激を受け、よりホットなイメージを追求したラフスケッチ


ベース車が2代目Σに変わって最初のクレイモデル
―― 空力と面処理
メディアでは当初から空力を考慮していたように書かれていたが、もう書いてもよかろう。実はデザイン開発時点では空力のセオリーをよく理解しておらず、「スポーツカーっぽくてカッコ良いんじゃない?」という理由で、プランビューでの絞り込みを強めに設定していた。しかしこれが後になって効果的であることを知った。後にスーパースラントノーズと名付けられたデザインも視覚的なインパクトを狙ったものでしかなかったのである。フロント部分はもっと絞り込みたかったが「レイアウトが成立しない」という理由で諦めてしまった。それにも関わらず計測結果は意外に良かったが、最初から詳しければもっと良くできたかも知れない。
また特徴的なノーズを強調するため、極薄のグリルとしたが、冷却風量の不足を理由に開口部の拡大を要求されることが懸念された。それを覚悟しいかにしてイメージを崩さずに対応するか頭を悩ましていたが、バンパー下部からの空気流入でOKという意外な検討結果で、初期イメージがそのまま生産車につながったことはうれしい誤算であった。
リヤ部分も絞り込みを強め「スポーツカーっぽくなって来た」と、担当者同志で自画自賛していたが、久保社長にモデルをプレゼンテーションすると「こんなナマズみたいなのはダメだ!」と一蹴されてしまった。それでは、とボディの絞り込みを弱める一方でクオーターガラスを絞り込み、ダックテールに繋がる広い面を作ってナマズイメージの排除に務めた。「これでナマズとは言われないだろう」と次のプレゼンテーションに臨んだのであるが、社長はそこをペンペンと叩き「この棚はイカン、だいたい君たちは次元が低いんだよ。もっと次元が高い面処理をしろ!」と、言い放ったのである。「君たちはセンスが悪い」は、時折耳にしていたが、「次元が…」には参った。「次元が高い面処理って…」と皆で頭を捻ったものである。なんとか生産車につながる形状を作り上げ、社長承認を得たのであるが、果たして次元は高かったのだろうか。

リヤを絞り込んだ結果、ナマズと評されたデザイン

―― 贅沢なデザイン
当時の北米法規ではパッシブシートベルトの装備が義務付けられており、ドア後端上部にアンカーポイントを設ける設計案が浮上した。これと「Bピラーは通常と逆の傾斜のほうが特徴が出る」という社長意見との相性が良く、それまでのサッシュレス案は中止し、Bピラーの逆傾斜に合わせた一体プレスドアを採用することになった。このデザインによってドア下部の後端を前進させ、開閉時の軌跡の拡大を抑えることが出来たが、それでも大型化したドアによる乗降性悪化が問題となった。ボディ設計は開閉時にドア前端が外側に出るダブルピボットヒンジを採用することでこれを改善した。

意匠課内のデザイン検討会での筆者(手前)


テープドローイングで様々なドアやクオーターパネルを検討
キャビン後半は細いCピラー+ガラスハッチ の構成としたが、開口部がガラス後端になると積載性が悪化するのが難点だった。開口部後退のために単純にガラス後端にダックテールをつないでもシール面が連続しないのでNGとなる。この問題にボディ設計は驚きの解決策を示した。ダックテールの裏面にガラスを通し、その後端を下向きに折り曲げることでシール面を連続させ、開口部の後退と共に高さも下げたのである。外観では判らないがダックテールは曲げたガラスの上に載っているのである。ドアにしろ、リヤゲートにしろ、見えない部分に コストを掛けるのは英断であったと思う。そして私にとっては、スタイル優先で随分気持ちよく贅沢をさせてもらったと思う。

何台ものモデル製作でお世話になったモデラーの方々
―― ノッチバックモデル
あまり知られていないことだが、開発途中で、ファストバックをベースにノッチバックを作り、当時あったカープラザ店で販売することが決定された。これは当時人気のプレリュードやシルビア(両車ともノッチバック)への対抗を意図したものであった。開発初期はサッシュレスドアで進めていたため、ルーフラインを含んだデザインの自由度があったが、一体プレスドア化でそうはいかなくなってしまった。特徴的なドアだったのでデザインがまとまるのか心配したが、担当した貝淵さんはリヤウインドウにシャープベントガラスを用い、他に類のないユニークな形状でまとめ上げた。社内ではこちらのほうに魅力を感じた人も多かったようだが、発売されていたらどうなっていただろうか。

プラザ店向けに計画されたノッチバックモデル
―― 発売の1年延期
デザイン決定後の開発は順調に進んでいたが、思いがけない出来事が起こった。1978年に勃発した第二次石油ショックである。これにより「ターボなどとんでもない」といった世相となり、1981年の発売予定が凍結されてしまったのである。前途を心配したが影響はそれほど長くは続かず1982年3月、国内に先立ちジュネーブショーでの発表となった。想定コンペティターはポルシェ924ターボで、会社としては相当な気合の入れようであった。 しかしその一方でノッチバックモデルは中止になってしまった。他車と十分以上に戦えるポテンシャルを持っていたと思うだけに実に残念だった。

ポルシェ924ターボ 画像提供:Motor Fan/CARSTYLING
発表が1年早ければスーパースラントノーズに類するデザインは、ほぼ存在せず大きな特徴になっていたと思う。しかし発売延期で他社から同様なものが出てしまった。同業者であれば1年程度で同様なものを生産化できないことは分かるであろうが、一般的には「マネ」としか受け取られず、これには悔しい思いをさせられた。
―― 心残り
当時は、前後のバンパーをつなぐ高さでボディサイドにピークラインを通すデザイン処理が主流であり、このプロジェクトでも当初からみなこの処理をしていた。私のデザイン案もそこは同じだったのだが、デザインを進めて行く内に、次第にこの処理では重心が低く見えて安定感が出過ぎてしまい、スポーツカーらしい「走りのイメージ」が不足していると感じるようになって来た。そこで色々な別案を試した結果、ピークラインの少し上にもう一本のキャラクターラインを入れることで、タンブルホームを強くしながら、視覚的な重心も上げて、ダイナミックでスポーティなイメージが出来上がった。ところがそのクレイモデルが出来上がると、今度はサイドのラインが多すぎる感じがしてきたので、思い切って低い方のラインは廃止しようと考えていたのだが、意外に早く承認されてしまい、その機会を逸してしまった。モデルの左右で作り分けておけば良かったと悔やんだが後の祭りである。作り分けても量産車の形状が選択されていたかもしれないが・・・。

筆者がこうしたいと考えていたスタイル
―― 振り返って考えると
筆者は幼少時から「想像図」を描くことが好きで、中学生の時には自分で考えた車の模型を作ったこともある。長ずるに及んでデザイナーとして自動車会社に潜り込むことになるのだが、この職業を選んだ人間であれば、一度はスポーツカーをデザインしたいと思うのではなかろうか。しかし、そこに至るには実力だけでは克服できない様々なハードルが存在し、望みが叶えられるチャンスはそう多くはない。自分の意志ではどうにもならない巡り合わせや、時の運に左右されるのはもちろん、例え開発メンバーになれたとしても自身の案が採用されるとは限らない。そんななか、スポーツカーに近い車で自分がやりたいことの多くを表現できたのは、改めて考えると実に幸運なことだったと思う。在職中はこの車以外にも様々な車種に携わったが、一番印象深いのはSTARIONである。
ハイテクイメージにチャレンジ
伊藤敏博
―― デザインのスタート
スタリオンは国内と北米を主な市場とするスポーツ車として企画されたが、当初はその中身の具体的な性格付けがなかなか定まらなかった。しかし、最終的にはECIターボエンジンを搭載し、ポルシェにも肩を並べる高性能でスペシャルティなスポーツカーという商品企画がまとまった。1978年中頃に基本レイアウトが固まり、エクステリアデザインがある程度具体化し、インテリアデザインのベースとなるウインドシールドラインやベルトラインが固まったところで、ようやく私たちは本格的にインテリアデザインに取り掛かることが出来た。
―― ハイテクイメージ
それまでの三菱のスポーツ車は、ギャランGTOに始まり、それに続くギャランクーペFTO、ランサーセレステ、ギャランラムダがあった。スタリオンと並行して販売される2代目ギャランラムダは、一層2ドアクーペとしての性格が強まり、その結果、スタリオンはエクステア、インテリア共に、よりスポーツカー的な方向を目指す必然性が感じられた。そこで、インパネデザインは、運転席周りへの機能の集中化を図り、高い操作性と視認性を実現することとし、フロントシートは、可能な限りホールド性を高め、安心、安全にドライブを楽しめることを目標とした。また、インテリア全体にハイテク感を感じさせる雰囲気を目指した。このハイテクという言葉は、ちょうどこの仕事に携わっている1970年代後半ごろに世界で広まった。自動車業界でもアナログ的な技術からエレクトロニクスを用いた技術への進化が大いに加速した時代で、そこは当時の日本が得意とする分野でもあった。そこで、ハイテクなデザインは欧米の車に対してこの車の大きな特徴付けになると考えた。

当初に行った幅広いアイデア展開

―― 「フローティングインパネ」
計器盤デザインでは、様々なアイデアスケッチを展開し、その中から計器盤上面部を低くして、メータークラスター周りに機能部品を集中させた案の評価が高く、その方向にデザインが絞り込まれた。このデザインは、棚の上にメータークラスターが浮かんだ印象であることから、我々はこれを「フローティングインパネ」と呼ぶようなり、目指すデザインイメージが明確になった。しかし、当初のアイデアスケッチではフローティングのイメージをハッキリと出していたのだが、その後具体化に向けた設計との詰めの段階では、成型性などの技術的な理由で妥協せざるをえず、最終的にはイメージが少々薄れてしまったことは、いま思い返すと残念だ。

フローティングインパネのデザイン検討
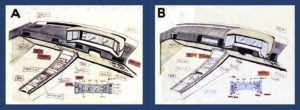
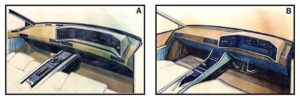
当初のアイデアスケッチとレンダリング
このインパネデザインで最も深く考えたのは、ドライバーにとってのメータークラスター周りのあり方だった。視認性、操作性に加えて先進的でハイテクなイメージでどうやってまとめるかに苦心した。具体的には、ワイドなメータークラスターの両脇にライティングやハザードなど6つのスイッチを配置した。これはステアリングホイールの直ぐ先にスイッチがあることで操作性に優れているのだが、実際に試してみると、遠すぎても、近すぎても操作感が良くなく、その最適な位置を見つけ出すために、実験部門や設計部門との調整には多くの時間を費やした。また、これらのスイッチには、ハイテク感を出すために電子音付きのタッチ式スイッチを提案したのだが、操作感がないので不安に感じるだろうとの理由で不採用となり、従来の機械式になってしまった。しかしその後タッチ式スイッチは広く普及したので、時代がもう少し後ならば採用されていたかもしれない。

初期段階のインテリアモデル

生産車のインテリア

協力会社で製作されたインテリアモデル
―― 実現しなかったブラックフェイス
メーターは、そのころ他車にまだ採用例がない液晶式電子メーターが上級仕様車に設定され、標準はアナログメーターとなった。このアナログメーターに、私は透過照明式のブラックフェイスメーターのアイデアを提案した。これは、真っ黒なメーターパネルが、キーをオンにすると同時に文字盤が発光するものであり、当時世界に例がなかった。私は、メーターの中に蛍光灯を仕込んだこの試作モデルを計画し、それをインテリア承認モデルに組み込んでプレゼンテーションした。するとその演出効果は抜群で、展示は大成功となり大いに喜んだ。しかし、その後の検討の結果、コストが高すぎるということで結局は不採用となり、私の努力は報われなかった。しかし、スタリオン発売7年後の1989年になって、トヨタ・セルシオでこのブラックフェイスメーターは世界で初めて世に出た。いまだに、あの時採用されなかったのが残念に思う。
私はさらに、メータークラスターを特徴付けるため、クラスター表面をスエード調に見せる植毛塗装に着目し、実現化に向けて設計やベンダーと検討を進めた。プラスチックの硬い表面よりもスエードのソフト感で、上質な雰囲気が出せると考えたのだ。これもインテリアモデルに反映したのだが、予想外に関係者の抵抗が強く、廃案となってしまった。今までにない見栄えは少々インパクトが強過ぎたようだ。
―― 「フルサポートシート」
このインテリアをデザインしている最中、1978年トリノオートショーに関連部門の方々と調査に出かけ、そこで見たルノー・サンクのスポーツモデルのスポーツシートがおもしろいということで、帰国後に購入した。我々はそのシートなどをデザインや設計の参考としながら、どのような体格にもフィットする「フルサポートシート」という新しいシートの構想を作り上げた。このシートは、着座した人の体格に合わせ、様々な部分を最適にサポートすることが可能なデザインが目標だった。

シートのアイデアスケッチ
始めに、発泡スチロールのデザイン検討用モデルを作製し、それを元にデザイン、設計、ベンダーの三者で実現性の検討を幾度となく行った。その上で試作シートを作製し、実際に座った時のホールド性や、乗降性の確認と改良を重ねて行なった。また、それまでにない特徴的な形状であるため、シート生地の縫製の検討も繰り返し行なった。こうして、初めはかなり高い目標と思われた「フルサポートシート」であったが、最終的には6通りの調整が可能なシートとして満足のいくデザインに仕上がった。それは、設計やベンダーの理解と協力があっての事だと感謝している。
その他、足元をスッキリさせるためのスライドレールの一本化、出入り性の楽な回転シート、助手席で快適なフットレスト、機能操作部品の電動化等、様々な提案をしたが、構造、重量、コスト面で多くは断念する事になった。

―― 信頼関係
いま当時を振り返ってみると、スタリオンのインテリアでは少々欲張り過ぎというぐらいに色々な事にチャレンジした。ブラックフェイスメーターを初めとして、思い通りにならなかった事も数多かったが、何事も先ずはとにかくやってみなければ分からないものであり、やりたい事が多いのは決して悪い事ではないと思っている。そして、新しいものを実現化するには、一緒に開発に関連する人々との結び付きから生まれる強い信頼関係が大切だと、改めて思う。
2021年11月