混沌から生まれた明快デザイン
三橋 慎一
―― 新社長の第一声
1973年6月、三菱自動車工業(株)の2代目社長、久保富夫さんが、就任早々デザインスタジオに来られるというので、皆並んで待っていた。三菱重工時代に自動車部門を率いた人だけに「またこってりしぼられるぞ」という予感がした。
意匠課のデザイナー達を前にして、久保さんの第一声は、「これからは俺がデザインを決める」だった。それまでは、企画部門、開発部門、営業部門などの幹部の合議制でデザインは決められていたのだが、久保さんは「デザインは俺に任せろ」と宣言されたのだ。いきなりのこの言葉に、私を含めその場全員の神経が久保さんに集まった気がした。それに続いて、叱咤激励の声が飛んだ。「先ずはデザインだ。技術はカネと時間がかかる。デザインは知恵とセンスがあれば出来るんだ」、「君たちは営業の意見を聞きすぎる。もっと自信をもってやれ」。どうやら発表したばかりのニューギャランが、角がとれ丸くなったことにご立腹の様子だった。「君たちは人のやれないことをやれ。創造こそが人間の存在価値だ」と続いた。これが久保新社長とデザイン部門との熱い関係の始まりであった。
―― デザインの方向付け
翌日から、ギャランシグマのデザイン作業は総力体制で始まった。最初の検討会では6案のレンダリングが提案されたが、その中から私が描いた案に方向付けされた。私がこの案に託した狙いは、初代コルトギャランの継承と発展だった。評価の高かったスポーティセダンの魅力をさらに発展させたかったのである。サイドビューは初代のイメージを頭に留めつつ、寸度的に有利な条件を活かして伸びやかさと安定感を表現した。当時のセダンの常識であるボックス・オン・ボックスの造形から脱したセミファストバック、ベルトラインを下にえぐりとった6角形のウインドウグラフィック、低く抑えたリヤのホイールアーチとその上をリヤエンドまで一直線に走るサイドラインなどで、特徴を持たせた。

筆者の提案スケッチ

最初の1/1クレイモデル
デザインの方向性は決まったものの、フルサイズモデル移行後は苦難の道が待っていた。重要なプロジェクトだけに、選択の巾を広げておく必要があり、久保さんは、当時世界のカーデザインの頂点に立つジュジャーロ氏にもデザイン提案を依頼した。送られてきたモデルは抑制の利いた端正なデザインで、見事にバランスを取った造形はさすがジュジャーロ氏と言えるものだった。しかし私の勝手な推測だが、恐らく久保さんは、トヨタ、日産の後を追いかける三菱として国内での存在感を出すには、これではまとまり過ぎていると考えたのであろう、彼への依頼はそこで打ち切られることとなった。一方、我々意匠課内ではシックスライト案やノッチバック案など、過去に類のない7案ものモデルを次々にトライした。しかし、久保さんの反応は悪かった。スタジオに来るたびに「こんな、ろくでもないもんしか出来んのかね」と罵り、機嫌が悪いとモデルを足蹴にされる。

6ライトのE案(左)とノッチバックの強いF案(右)
 |
最初の1/1モデルから発展したG案 |
 |

愛用の指示棒でデザインにダメ出しをする久保社長
―― 混沌の中の荒療治
そこで、この状況から抜け出すために、仕切り直しをして新しいアプローチを試みようという意見が持ち上がった。それは、基本寸度図(開発初期に設定する、全長、全幅、全高などの寸度を含む車全体のレイアウト図)の条件を外して理想的なプロポーションを追求したイメージモデルを作ることであった。そこで、最初に選ばれたデザインの発展型モデルをベースとし、それを担当していた貝淵龍君を先頭に、皆でその荒療治にとりかかった。クレイのぜい肉を削り落とし、プロポーションや量感を見るだけの簡潔なイメージモデルが出来上がった。このモデルは、全高を下げたおかげでボディサイドに強いタンブルホームとターンアンダーが生まれ、スリーボックスやボックス・オン・ボックスの概念から離れて、全体をひとつの塊とした造形(モノリシック・フォルムと名付けた)となった。いわば最初に方向付けされたスケッチのイメージに戻ったと言っても良く、ここでそれがようやく具現化した。

基本寸度を度外視して片側を削ったイメージモデル
1974年4月のある日、久保さんが久しぶりにスタジオに入って来られた。数ある進行中のモデルには目もくれず、片隅に置いてあったイメージモデルを目ざとく見つけた。「これがいいね。これをベースに進めたらどうだ」この一言でやっと前途に光明が見え、我々は混沌としていた状態からようやく抜け出すことができたのであった。

基本寸度が見直されスタイリッシュになった最終ステージのクレイモデル
―― ゴール前の試練
イメージモデルで久保社長のお墨付きをいただいたことで、全高は25mm下げて1360mmにするることになったが、デザインのために基本寸度図を開発途中で大きく見直すのは私の経験では初めての事だった。しかし、このロー&ワイドのデザインは、居住性を悪化させたので、「これではまるで4ドアクーペではないか」と非難する人もいた。けれども、この頃既に国内では4ドアハードトップが出現し始めており、この他社にないスポーティでスタイリッシュなセダンの方向は、一歩先を行くために必要な道だと思った。
その後は、中川多喜夫君をリーダーとするチームに仕上げのステージはゆだねられ、フロント周りは本多潔君、リヤ周りは片山松夫君、全体は中川君が担当して、既に遅れに遅れていた日程を挽回すべく、最後まで粘り強く頑張った。
 |
ようやく承認を得ることができた I 案モデル。この後ディテールの仕上げへと進む |
 |

本多潔氏のフロントビュースケッチ
ところが困ったことに、最後の生産準備に入った段階でも、久保さんは平気で細かい注文を出して来た。「君ね、ここは少し単調だ。これで終わるのは素人のやることだ」と言いながら自らモデルを削ろうとさえするのだ。そして1974年の暮れも押し詰まったある日、フロントのコーナーランプの処理が気に入らないのでやり直せとの指示が出た。しかし、いかんせん時間は切迫していた。仕方なく一部のスタッフには正月休みを返上し作業してもらうことにした。社員にとって、正月は家族とともに過ごす貴重な休日だ。当人たちが帰省も諦めて「やりましょう」と言ってくれたのはありがたかったが、難関は組合(労組)への説得だった。「元旦から社員に働かせるとは何事か」、組合幹部は真赤な顔で私を非難した。開発日程は大幅に遅れ、後に控える設計や生産部門からは、「デザインのせいで日程が遅れる」と不満が続出し、協力的だった身内のモデラー達からも面と向かって嫌みを言われる始末。まさに四面楚歌だった。

苦楽を共にしたデザイナー、モデラー、スタジオエンジニアらのチーム。前列中央が筆者
このように、私には厳しい試練と苦しい思い出しかないプロジェクトだったが、1976年の5月には「シグマ」と命名され、晴れて発売することが出来た。なかでも市場の上級志向に向け、フロントグリルや高級内装で差別化した「スーパーサルーン」に注目が集まったのは、あまり期待していなかっただけにありがたかった。いずれにしろ「シグマ」は名の通り、会社の総力を結集したプロジェクトだったのだが、デザインは初代コルトギャランへの原点回帰だと言う評価もあり、他社の同業者や販社の方々からも、お褒めの言葉をいただいたのは大変嬉しかった。

スーパーサルーンの内外一体FRPモデル
―― 含蓄のある久保語録
最後に、この開発の主人公とでも言うべき久保さんが『カーグラフィック』誌の取材に応じて語られた久保語録を抜粋して紹介しておきたい。
「カタチだけよくてもなんの意味もない。技術に裏付けられたスタイリングでないと・・・。そこがわれわれの技術製品の特徴であり面白さだ。というわけで若い連中とやりに岡崎に行くわけだ。勝手放題なことを言って帰ってくると、うまくやってくれる。これは私に出来んと思うことでも絶対やれと言ってくる。まあスッタモンダで時間が遅れる。しかし最初決めたデザインが悪かったら永久に悪いクルマが出てくるのだから、最初が無限に重要なのだと。最初遅れても良い。だんだん遅れて、じゃもうこれで良かろうと言うときに、はじめからの予定でやるぞ、と言うからみんな泣くわけだ。それでもみんな頑張る。社長業より設計やってたほうがずっと面白い」
この語録で分かるように、厳しさの中に明るさとほのぼのした優しさを持った人だった。褒められたことは一度もなく、叱られてばかりいた我々だったが、不思議に憎めない人で、その人柄と良いデザインの車を作るという意思に強く惹き付けられていた。ものを創造するという基本的なところでつながっていたからであろう。
|
|
久保社長と社長就任後の第一作となる |
2022年5月
モダンで上質なインテリア
岡本 治男
―― 新しい上級志向
1970年代初め、市場ではセダンからの派生車種が揃い、ユーザーは自身の生活に見合ったタイプの車で楽しむことが定着してきた。また、2台、3台車を乗り継いだ人が増えてくる中で、ユーザーの目は見た目や走行性能のほか、使い勝手や便利機能、安全対策などにも関心が向き始め、一ランク上の車格を望むようになってきていた。こうしたなか、これまでのギャランユーザーの上級志向を狙ってギャランシグマの開発が始まった。
三菱は、初代コルトギャランを豪華にドレスアップしたニューギャランを1973年に発売したが、その評価は期待には及ばなかった。この結果は、上級志向に求められるものとは、見た目の豪華さ、ノスタルジックな高級感などではなく、解放感、上質感、安心感というイメージではないかと、見方を変える方向を気付かせてくれたものだった。
―― インテリアスタジオ最初の仕事
1973年に私たちの意匠課で大きな組織変更があり、新たにインテリアスタジオができた。インテリアデザイナー達が一つのスタジオに集まり、様々な専門的知識やノウハウを共有するとともに、機種間で共用する部品の横通しを行う等で、デザインのクオリティを上げるという狙いだった。ギャランシグマのインテリアはその最初の仕事となった。
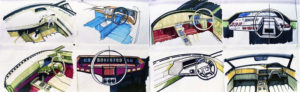
初期のラフスケッチ

アイデアスケッチとテープ図面でのデザイン検討
エクステリアデザインは相当な試行錯誤をしながら、革新的なスタイルを探っていた。インテリアデザインとしては、窓周りの形状や傾斜角度、フロントデッキやベルトラインの位置や高さは、関わりが深いので、大きな変更があるたびにどの様な影響があるかを常にチェックしながら進めた。一方、企画や設計部門からの要求として、計器盤は派生車(クーペやピックアップトラック)に大きな変更なく搭載できるものとしたいという要求が出てきた。このことはステアリング角度やアイレンジ位置に大きな差がある車種間への搭載を満足させるために、視認性や、操作性に関わる形状の検証に時間を割くこととなった。

当初は4案のクレイモデルでデザインの方向を模索
―― 雑談から生まれた「ワンパネルメーター」
インテリアデザインは各部門との関係や検討項目が多いことから、一番難易度の高い計器盤周りを若干先行して進め、「ワンパネルメーター」(複数のメーターが1枚パネルに見えるデザイン)を持つ棚式計器盤と、センターコンソール一体型計器盤の2案を提案した。検討会での評価は二分し、甲乙つけがたい状況であった。しかし最後は、この車の開発コンセプトとエクステリアデザインに合っているという我々デザイン部門の提案が通り、棚式計器盤に決定された。この計器盤は凝ったデザインで豪華さを出すのではなく、助手席同乗者に疎外感を与えず、ソフトでやさしく、明るく解放感のある雰囲気を醸し出すのが狙いであった。

ワンパネルメーターの棚式計器盤(左)と センターコンソール一体型計器盤(右)
このワンパネルメーターのアイデアはひょんなことから生まれた。初期段階のスケッチでは計器盤全体の形を取りあえず大まかにざっと描くために、メーター部分を省略して黒く塗りつぶすことが多かった。皆でそのスケッチを見ながらの雑談で、「こんな雰囲気も良いじゃないか」と言う声が出てきた。そこで、デザイン要素の一つとして検討しようとなったのだ。そうした描き方は他社でもやっているのではないかと思って調べてみたら案の定似たようなスケッチはあった。『誰も考えることは同じだな』と思いながら、やるなら早いもの勝ちだという事で具体化して行った。このメーターデザインは、丸メーター枠を上下カットし、内目盛り外数字で、書体は横長タイプとすることで、フードをあまり高くしなくても大きく見やすいものにすることが出来た。さらに、計器類を横方向にゆったりとレイアウトしたことで、今までにないワイド感と、クリーンで上質感のあるデザインに出来た。
計器盤全体は、横方向の連続感を強調したデザインにした上で、上級の仕様では上下をツートーンに配色して運転席と助手席の雰囲気に強い統一感を持たせた。また、低く設定されたベルトラインに棚の上面を合わせることで、計器盤上部のボリュームを抑え、室内の解放感を醸し出した。

最終の承認モデル
―― 予想を超えたスーパーサルーン
開発後半に追加されたスーパーサルーン仕様は当初月産500台の目標で開発された。計器盤はエア吹き出しグリルのメッキ化、無反射ガラスのスモーク化によるワンパネルイメージの強化、シート生地はジャガード織りとし、ドアアームレストも灰皿やドアランプを組み込んだ大型のものを追加した。月産500台分生産できれば良いということで、これに見合った製法(単価は高くなっても設備投資が少なくてすむ)でデザインを行った。当時月産800~1,000台付近が製法を見極める境界であったと記憶している。ところが、この仕様は発売後予想を大きく超える好評を博し、増産に踏み切らざるを得なくなった。もともとが少量向け製法であったため、ベンダーや購買部門は対応が大変であったようである。

スーパーサルーンのデザイン検討

スーパーサルーンの計器盤

スーパーサルーンのリヤシート
―― 五感で感じるインテリア
ギャランシグマはサイレントシャフトによる静粛性を始めとした様々な新技術、新機構などにより、発売後大変に好評で、特にデザイン面では競合する他車と異なる独自性や明快なイメージが評価されていたと思う。私たちがデザインしたインテリアも、ヨーロッパ調で明るく開放感のある雰囲気が高く評価されたことで、当初の狙いが達成されたのだと感じた。
インテリアはエクステリアに比べて人の感じ方が異なり、五感で感じる度合いがとても高いと私は思っている。見た目の形に留まらず、表面の風合い、手触り、座り心地、操作する時の音やフィーリングなど、様々な事がインテリアの印象として人に伝わってくる。車という小さな空間の中で、そうした五感を通じて、いかに疲れず、心地良く、快適に過ごすことが出来るかを、自分は意識ししながらデザインをしてきた様に思う。
2021年11月
